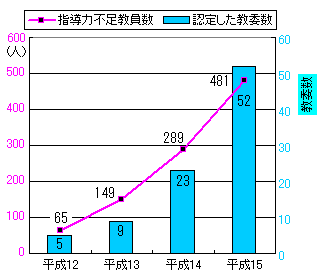 5月1日のある新聞の1面トップは、
5月1日のある新聞の1面トップは、「指導力不足教員 最悪481人」「前年度
比1.6倍」という見出しの記事でした。
右のグラフは、その記事に添えられて
いたグラフを元に、私が作成しなおした
たものです。青い柱状グラフは、指導力
不足の教員を認定した教育委員会の数を
表しています。
それでは問題です。ジャン!
Q この記事の見出しは正しいでしょ
うか?
A 正しくない。
理由は、即日、私がその新聞社に投書した文章で示します。(多分、ボツ)
Top Page へ 前へ 次へ複眼 数学・理科ネタ 01 005号(2004年5月6日)より
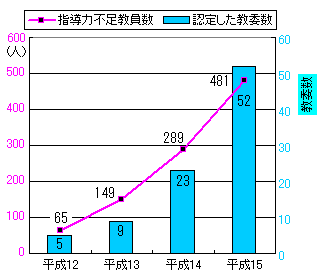 5月1日のある新聞の1面トップは、
5月1日のある新聞の1面トップは、「指導力不足教員 最悪481人」「前年度 比1.6倍」という見出しの記事でした。 右のグラフは、その記事に添えられて いたグラフを元に、私が作成しなおした たものです。青い柱状グラフは、指導力 不足の教員を認定した教育委員会の数を 表しています。 それでは問題です。ジャン! Q この記事の見出しは正しいでしょ うか? A 正しくない。 理由は、即日、私がその新聞社に投書した文章で示します。(多分、ボツ) |
|
五月一日の「指導力不 足教員最悪四八一人 前 年度比一・六倍」という 記事について、数学の教 員として述べさせていた だきます。 記事には、教委が認定 した指導力不足教員数の 推移を示す折れ線グラフ と、その数を調査した教 委数の柱状グラフが添え てあります。 |
これによれば「調査し た教委数は前年度比二・ 二倍なのに、報告された 該当教員数は一・六倍に しかならない」のです。 さらに、一教委あたり の指導力不足教員数は、 平成十二年度は十三人、 十五年度は九・二五人で すから、問題の教員数が 増加しているという解釈 は明らかに誤りです。 |
調査地域を増やせば人 数も増えるに決まってい ます。実数と比率を混ぜ こぜにするなというのは 統計の初歩です。 報道関係者は、報道が 国民に与える影響の大き さを改めて自覚し、統計 資料を思い込みで解釈せ ず、客観的な資料の読み 方をしっかり勉強しても らいたいと思います。 |
Top Page へ 前へ 次へ 先頭へ