引き算の順序 〜a−b か b−a か?〜
話のキッカケまずは、教科書の記述を見てください。
[高校の教科書の記述]
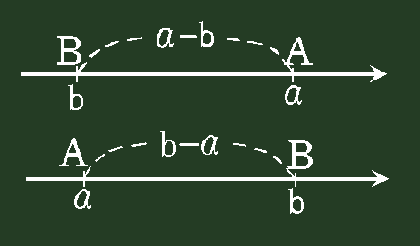 数直線上の2点A(a),B(b)間の距離ABは
数直線上の2点A(a),B(b)間の距離ABはa≧b のとき,AB=a−b a<b のとき,AB=b−a であるから AB=|b−a| と表すことができる。 |
これを見て、疑問に思いませんか?
なぜ、
AB=|a−b| … (1)
ではなく
AB=|b−a| … (2)
なのか? と。
|a−b|=|b−a| なのだからどちらでも良い。ならば、(1)のようにアルファベッ
ト順の方が良さそうだとは思いませんか? あるいは、左辺のアルファベットの順と揃え
ておく方が良いと思いませんか?
しかし、どの教科書、参考書、専門書を見ても、例外なく(2)の書き方になっています。
一時的に併記してあるものもありますが、その後のページでは、(2)に統一してあります。
(2)は、左辺のアルファベットと逆順に引くというもので、
BA=|a−b| … (3)
とするという取り決めです。
これには何か理由がありそうです。
ここでは、この「引き算の順序」について、
「差」の考え方
2つの数「aとbの差」といった場合、2通りの考えがあります。
ひとつは、
a>b のとき a−b … (4)
a<b のとき b−a … (5)
a=b のとき 0 … (6)
というように、常に大きい方から小さい方を引くという、不等号による表現を別にすれば、
小学生でも理解できる(はずの)ものです。
この考え方では、aとbの大小を先に判断して、その次に、大きい方から小さい方を引
いて、大きい方は小さい方よりどれだけ大きいか、あるいは、小さい方は大きい方よりど
れだけ小さいかということを計算します。
私たちの日常は、このように考えていると思います。
実はこれは、「学校の数学 001」で扱った絶対値と本質的に同じことです。つまり、
aとbの差は |a−b| である … (7)
というわけです。
aとbの差は |b−a| である … (8)
と言っても結果は同じです。
上記の(4)と(5)の場合分けは、引き算の結果を正の数にするためのものであり、これ
即ち、a−b の値の絶対値を考えているということです。
もうひとつは、aとbの大小にかかわらず、
a−b … (9)
で済ませてしまうやり方です。これは、
b−a … (10)
とする場合もあります。
(9)と(10)の違いは、aとbのどちらを基準にするかの違いです。
a−b は bを基準にしたaの差 \ … (★) b−a は aを基準にしたbの差 /となっているのです。
(9)は、bを基準としてaの大小を計算しています。
a−b>0 なら a>b 「aはbよりも大きい」
a−b<0 なら a<b 「aはbよりも小さい」
a−b=0 なら a=b 「aはbに等しい」
です。
(10)は、aを基準にしたbの大小を表します。
b−a>0 なら b>a 「bはaよりも大きい」
b−a<0 なら b<a 「bはaよりも小さい」
b−a=0 なら b=a 「bはaに等しい」
です。
この(9)または(10)は、日常の私たちの頭の中の計算とも異なりますが、ひとつ目の方
法との決定的な違いは、aとbの大小関係を引き算の前に判断するのではなく、計算の結
果の中にaとbの大小関係も現れるという点です。
つまり、引き算の結果が正の数の場合には「多い」とか「増加した」という言葉に、負
の場合には「少ない」とか「減少した」という言葉に結びつけることができるということ
です。
このやり方は、基準にするものを明確に決めて差や変化を表現するのに適しています。
このようなとき、引き算の順序は重要です。
もちろんこれは、負の数を学んだ後でないと使えません。
引き算の順序
小学校以来、引き算は大きい方から小さい方を引くということで、日常生活の中でもそ
のようにしていますが、実は、中学校で負の数を学んだ後は、上の(★)のような引き算の
順序について、改めて認識し直さなければなかったのです。
中学校ではそこをきちんと意識して授業をしているでしょうか。
それでは、冒頭の教科書の記述例をもう一度考察します。
そこでは、数直線上の2点A,B間の「距離」を問題にしているので、負にならないよ
うに計算する必要があったわけですが、たとえば、点Aから見て(Aを基準にして)点B
がどこにあるかを言い表すには、それぞれの座標a,bを用いて
b−a
と計算して、
点Bは、点Aから数直線上を b−a だけ行ったところにある
と言えばよいことになります。
この「b−a」は、AからBまでの「距離」だけではなく、「方向」も含んでいること
に注目します。つまり、数直線の正の方向が右だとすると、
b−a>0 のとき、BはAの右側(数直線の正の方向側)
b−a<0 のとき、BはAの左側(数直線の負の方向側)
という具合です。
[例1]
|
A(3),B(5)の場合 Aから見てBは、5−3=2 として、正の方向に 2 だけ行ったところにある Bから見てAは、3−5=−2 として、負の方向に 2 だけ行ったところにある 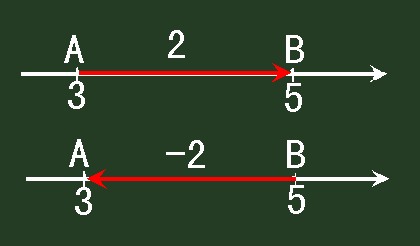 単にAとBを結んだ線分を書くのではなく、右図のよう
単にAとBを結んだ線分を書くのではなく、右図のように、Aが基準ならAからBまでの矢印、Bが基準ならBか らAまでの矢印にすると大変分かりやすくなります。 |
数学では、向きの付けられた線分を 有向線分 といいます。
点AからBへ向かう有向線分を
 と書くことにします。
と書くことにします。BからAなら
 と書きます。
と書きます。有向線分の始まりの点を 始点、終わりの点を 終点 といいます。
有向線分の差
数の加法や減法を、数直線上の有向線分を用いて視覚的(visual)に表現してみます。
まず準備として、例えばA(5)とすると、「5」という値を有向線分
 で表すこと
で表すことにします。つまり、「5」を表す点Aは、原点Oからこの向きにこれだけの距離の所にあ
るということを視覚的に表そうというわけです。
B(−3)なら、
 とは逆向きで長さが 3 の有向線分
とは逆向きで長さが 3 の有向線分  になります。
になります。
[例2](加法)
5+2=7 は、「5」を表す有向線分  の終点Bに「2」を表す有向線分 の終点Bに「2」を表す有向線分  を平行 を平行移動して繋げた結果としてできる有向線分  の終点で示される。 の終点で示される。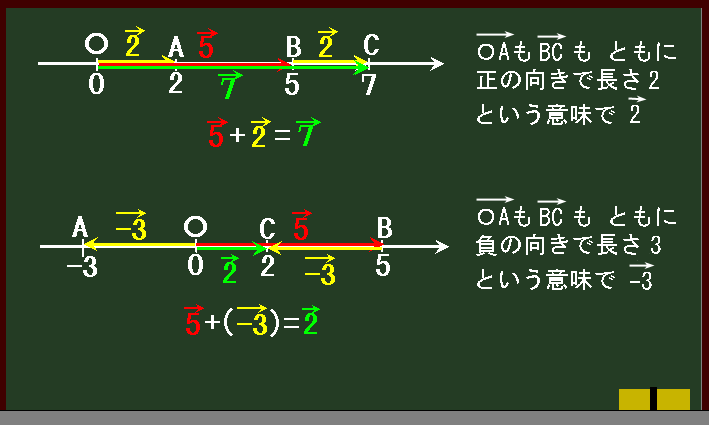
5+(−3)=2 の場合、「5」を表す有向線分  の終点Bに「−3」を表す有向線分 の終点Bに「−3」を表す有向線分 を平行移動して繋げた結果としてできる有向線分 を平行移動して繋げた結果としてできる有向線分  の終点で示される。 の終点で示される。 |
黒板に突然、数字の上に矢印を乗っけたヘンな記号を書きましたが、これは、有向線分
のある位置によらずに、同じ向き、同じ長さの有向線分を同一視しようと思って、こうし
た書き方をしました。
有向線分をこのように平行移動して使っても、結果として矛盾は起こらないので、有向
線分の本質は、書いてある位置ではなく、向きと長さであることが理解できます。
[例3」(減法)
5−3=2 は、5=3+? として考える。つまり、「3」を表す有向線分  に、ある有 に、ある有向線分を繋げた結果としてできる有向線分が「5」を表す  になればよい。その「あ になればよい。その「ある有向線分は  で、「2」を表す有向線分と同等である。 で、「2」を表す有向線分と同等である。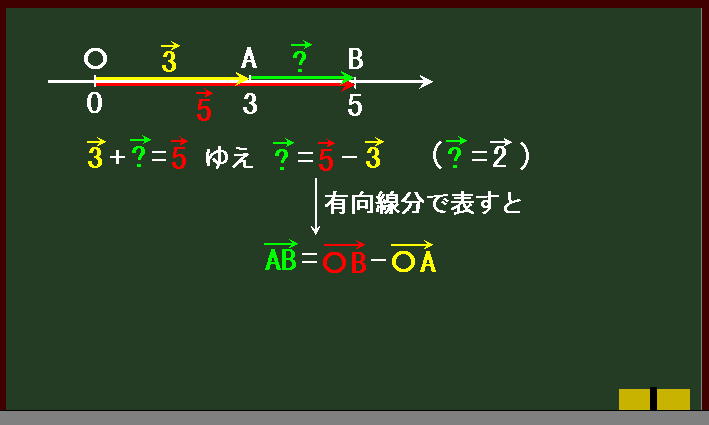
|
このように、2つの有向線分の差という形で引き算を見ると、
 =
= −
− 、 数値では b−a
、 数値では b−aという具合に、結果的に、線分を表すアルファベットの順と引き算の順序が逆になること
が分かります。
これはちょうど、
 と
と  の始点をそろえて背比べをしている状態です。まさに、
の始点をそろえて背比べをしている状態です。まさに、「差」を計っているわけです。
そして、向きについては、
 −
− ならAからBの方を見た状態
ならAからBの方を見た状態  になります。
になります。ですから、
 =
= −
− … (11)
… (11)であり、A(a),B(b)とすると、
AB=b−a
という記述になるわけです。
絶対値記号が付けば、|b−a|=|a−b| なので、どちらでもよいことになるのです
が、この、有向線分の差の式(11)の形の名残で、AB と来れば b−a とすることが
この "業界" の習わしになっているのです。
このページの先頭へ Top Page へ