〜無駄な公式 002〜
|
直線の方程式 [1] 異なる2点  ,
, を通る直線の方程式
を通る直線の方程式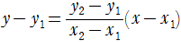
.gif) [2] 曲線  上の点
上の点.gif) における接線の方程式
における接線の方程式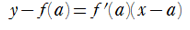 |
これらを別々の公式として暗記することは、数学をつまらなくするだけです。
これらの公式のおおもとをきちんと押さえて、上の二つはその応用であることを理解す
れば、暗記など必要ないのです。その意味で、これらを無駄な公式としたのです。
|
おおもとの公式 [0] 点  を通り、傾きが
を通り、傾きが の直線の方程式
の直線の方程式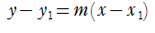
|
[1] について
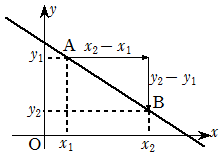
|
 のときは、2点の座標から直線の傾き
のときは、2点の座標から直線の傾き は計
は計算できます。


.gif)
これと点
 で、公式[0]を使えば良いのです。
で、公式[0]を使えば良いのです。教科書にもこのような説明は書いてはありますが、公式[1]を公式[0]と同列の扱いで四角で囲んだりするものです
から、皆さんの多くが、直線の公式は[0]と[1]の2本が別々に存在していて、場面に応じ
て使い分けなくてなならないのだというように受け取ってしまうのだと思います。
実際、[1]の分数の部分が直線の傾きなのだということもすっかり忘れて、ひたすら2
点の座標をポチポチと当てはめている生徒が多数います。
しかし、本質的には、[1]と[0]は同じものなのです。
むしろ、直線上の2点の座標から傾きを出すところだけをひとつの公式として独立させ
ておいた方が有用です。
なお、傾きの式において、分子分母の引く順序については、本シリーズの「002 引き算
の順序」で説明しています。
あと、点の座標として
 を用いても結果は同じになります。つまり、2点のう
を用いても結果は同じになります。つまり、2点のうちのどちらを用いても良いので、公式としては、
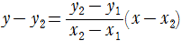
も併記しておくべきでしょうが、教科書にはその記述はありません。
皆さん、もし、問題がA,Bでなく、2点PとCを通る直線などとなっているとき、公
式中の
 にPとCのどちらを当てはめればよいのか、迷ったり不安になったりし
にPとCのどちらを当てはめればよいのか、迷ったり不安になったりしませんか。あるいはそのような経験はありませんか。
教員は、このことをきちんと補足をしてください。
[2] について
曲線
 上の点
上の点.gif) における接線の傾き
における接線の傾き は
は であり、当然、接点で
であり、当然、接点である
.gif) を通ります。したがって、点
を通ります。したがって、点.gif) を通り、傾き
を通り、傾き
 の直線と
の直線ということで公式[0]を適用すれば良いのです。
これも、[2]を独立した公式であるかのように四角に囲んだりするから、生徒は、また
公式が増えたという印象を持ってしまうのです。
皆さんの中には、場面に応じて[0][1][2]の3本の公式を使い分けるのだという感覚で
いる人も多いのではないでしょうか。
しかし、本質はそうではないのだ、[0]を基本にして、[1]や[2]は、傾きを別途求めて
[0]を適用するのだということをここで理解することができれば、きっと数学の学力はもっ
と伸びると思います。
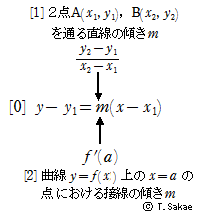
|
[1] に関する補足
[1]の分母を払うと
[3] 異なる2点 ,
, を通る直線の方程式
を通る直線の方程式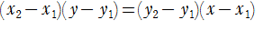 |
分母を払ったおかげで、
 という条件が必要なくなるのです。
という条件が必要なくなるのです。 の場合は、2点
の場合は、2点
 ,
, が
が 軸に対して垂直方向に並んでい
軸に対して垂直方向に並んでいるのですから、直線ABに傾きという概念は当てはめられず、したがって、傾きを使う
公式[1]では
 という制限がつくのです。
という制限がつくのです。それに対して[3]は、
 の場合にはちゃんと
の場合にはちゃんと が得られます。
が得られます。このときは当然、
 です。なぜなら、
です。なぜなら、 だと、AとBは同一の点になっ
だと、AとBは同一の点になってしまい、直線が定まらないからです。
公式[3]なら、[0]とは違う価値を持った公式として別に四角に囲って載せる価値がある
のです。