〜無駄な公式 003〜
累乗根の根号に関する計算公式
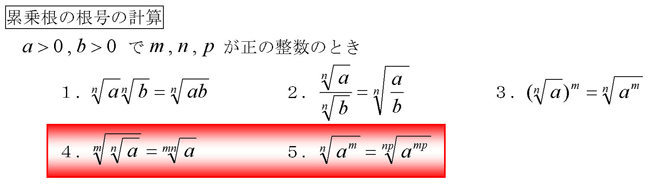
|
これは、指数関数の最初のところ、指数を分数に拡張する直前で学ぶようになっている
公式です。見るからにややこしそうでしょ?
ちなみに、根号
 は、
n=2 の場合には
は、
n=2 の場合には の左側の 2 を
省略して
の左側の 2 を
省略して と書きます。
と書きます。つまり、中学校で習った平方根なのであり、n=2 の場合の公式1,2,3は中学校で習っ
たはずのものです。(根号の左側の小さなnを消してみよ。)
また、n=3 の場合は3乗根(のうちの実数のもの)になりますが、これは立方根とも
いうということは、3次方程式を学ぶ際に出てきます。ただ、そこでは根号は出てきませ
ん。
さて、もう一度上の公式を見てください。
n=2 の場合に公式1,2,3が成り立つことを考えれば、n>2 の場合も同様のこと
が成り立つということで、さほど混乱は起こらないでしょう。
ここで「無駄な公式」として挙げたいのは、4と5です。赤で囲っておきました。
累乗根は、指数関数の学習中に出てくる話で、指数関数からすると根号の取り扱いは枝
葉の部分です。しかも、根号の計算練習をやった直後に、これらは指数法則ですべて統一
的に扱えるということを学ぶのですから、根号のところにとどまって練習を繰り返すのは
無駄である、という意味で、特に定着しにくい4と5を槍玉に挙げたのです。
根号の概略
一般に、
 を正の整数として、
を正の整数として、
 を満たす数
を満たす数
 を、
を、
 のn乗根といい、
のn乗根といい、2乗根、3乗根、… を一括して累乗根といいます。
n乗根のうち実数のもの、また、実数のものが正と負の二つある場合には正の方を
 と表します。
と表します。分数指数の定義
n乗根の根号と指数の関係は
|
|
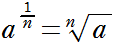 … ① … ① |
が基本です。これは、指数法則が成り立つように
 の意味を定義したのです。つまり、
の意味を定義したのです。つまり、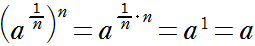
となるべきですから、
 とおくと
とおくと
∴

という具合です。ただし、ここでは話を複雑にしないために
 という制約をつけて
という制約をつけておきます。
この定義から
|
|
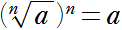 あるいは あるいは
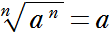 … ② … ② |
が成り立つことは明らかですね。
さて、分数指数を学習する際には、根号については、その定義①とそこから即座に得ら
れる②、そして、冒頭の公式のうちの1〜3だけ理解しておれば十分です。
それなのに、指数を分数に拡張する前に、根号の計算例題や練習として
(1)
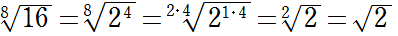
(2)

というような練習をするようになっています。
しかし、これらは、直後に学ぶ分数指数を用いれば、
(1)'
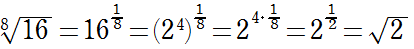
(2)'
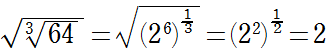
という具合に、指数法則を利用した方法に統一できるのです。
指数が主役のところですから、さっさと指数による計算に移り、根号だけで処理するこ
とに時間をかける必要はありません。
といっても、私は根号が不要だと言いたいわけでもないし、根号を悪者扱いするつもり
もありません。
根号は、累乗根という意味は分かりやすいわけで、先ほどの(2)においては、

なので
 .したがって
.したがって(1)''
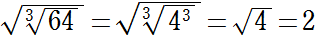
というやり方で、根号の理解を深めたいところです。
このページの先頭へ Top Page へ