~無駄な公式 004~
単位円単位円とは、
 平面における原点を中心とする半径 1 の円のことです。
平面における原点を中心とする半径 1 の円のことです。ところで、ここでの話は、無駄な「公式」というより、単位円を使わない方が分かりや
すいと思われるところでわざわざ単位円にこだわって説明しているという意味で、「無駄
な」というカテゴリーに入れて取り上げました。
さて、それでは、その場面を見てみましょう。内容は、数学Ⅰの三角比です。
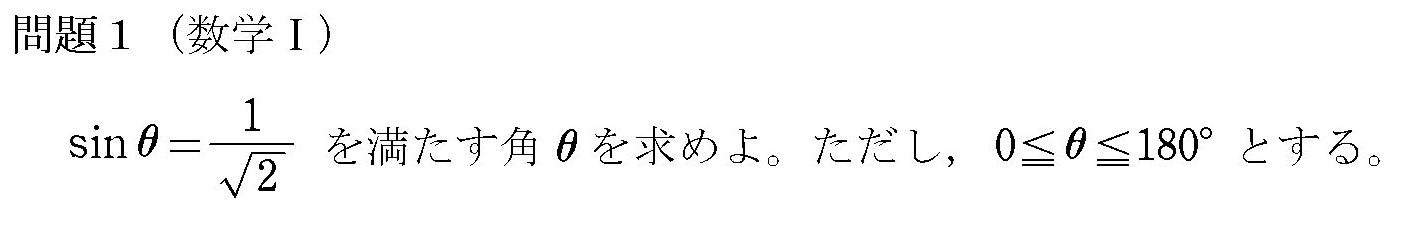
|
教科書は次のような解答を載せています。
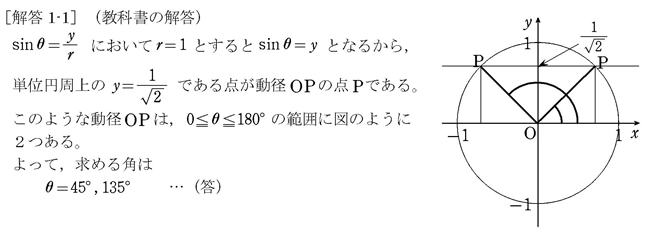
|
これに対して、私の授業での説明は、こうです。
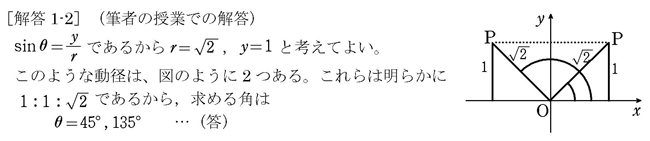
|
教科書と私の授業との違いは、単位円を使うか使わないかの違いです。
なぜ私は単位円を使わないかと言うと、上の解答1-1(教科書の解答)を見てください。
これの最大の難関は、y軸上の
 という目盛りの位置を見付けなければならない
という目盛りの位置を見付けなければならないことです。
それに対して、解答1-2では、中学校で学んだ「1:1:
 」に直結して、45°とい
」に直結して、45°という角度と結びつきやすいという利点があると、私は考えています。実際、生徒も納得しや
すいようです。
しかし、解答1-1の方法では、動径が2本あることが分かりやすいのに対して、解答1-2
では、それが分かりにくいという欠点があります。
この欠点を補うために、解答1-2においても原点を中心とする円を書いておきます。た
だし、半径は1とは限りません。
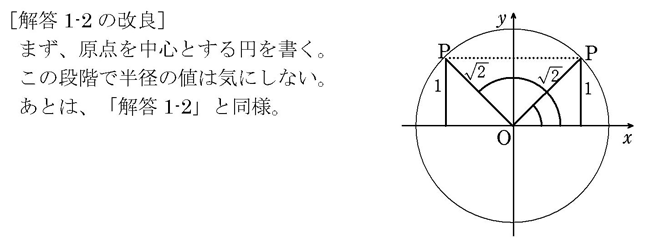
|
この問題の場合は、結果的に半径を
 と考えたことになります。
と考えたことになります。今度は円が書いてありますから、y座標が1になるところがy軸をはさんで左右対称な
位置にあることに気づきやすくなっています。
正接については、後日追加しますが、ともかく、この手の問題で単位円に固執する理由
はないということはおわかりいただけたでしょうか。
私は、体裁のよい説明よりも、生徒に必要のない負担をかけることのないような説明方
法を常に心がけています。
2009年10月29日追記
それでは、正接(tan)についても見てください。
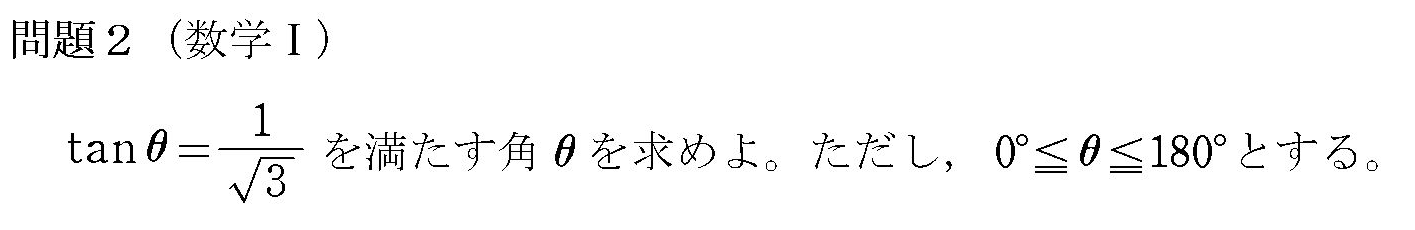
|
そしてまず、教科書の解答です。
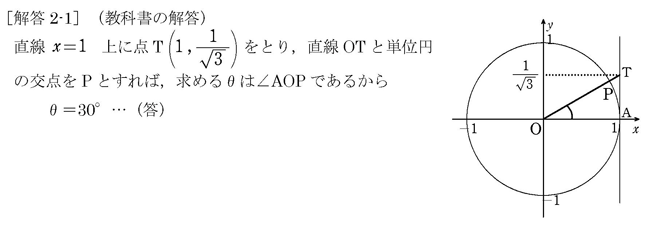
|
さて、この解答の中で、単位円はどのような役割を果たしているのでしょうか? わざ
わざ単位円周上に点Pをとらなくても、θ=∠AOT で話はできます。
それで、私の授業では、こうです。
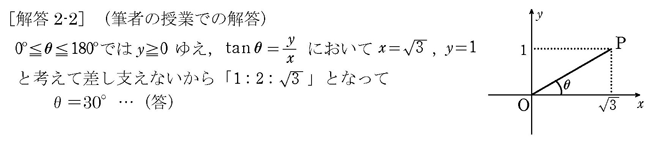
|
いかがですか。やはり単位円がないと困りますか?
教科書の方法では、
.gif) という座標の点を取ることの困難さと、「
という座標の点を取ることの困難さと、「 」
」につなげることの困難さを避けることができません。
それに対して私の方法は、簡単に「
 」とつながって、30°が導かれます。
」とつながって、30°が導かれます。なお、数学Ⅱからは動径の位置に制限なく三角関数が定義されますから、たとえば、
 (弧度法で表すと
(弧度法で表すと )という設定もあります。このようなときに
)という設定もあります。このようなときには次のように解答すればよいのです。
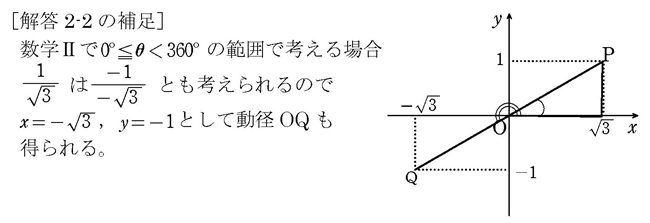
|
ともかく、単位円の出番はありません。
単位円は、三角関数(三角比)の値の変化を見ようというときに初めて使えばよいとい
うのが私の主張です。
最後に、数学Ⅰの教科書では「動径」という用語は使われず、必ず円または半円を描い
て「半径」と記述しているということを付け加えておきます。
このページの先頭へ Top Page へ