心と脳
話を戻して、脳の部位ごとの機能が研究され始めたのは、19世紀に入ってからです。そ
の頃、顕微鏡と細胞染色技術の進歩で、脳などの細胞組成の研究が可能になってきました。
また、1970年代以降、CT(computed tomography,コンピュータ連続断層撮影法)や
MRI(magnetic resonance imaging,磁気共鳴画像法)の技術が確立されてからは、体
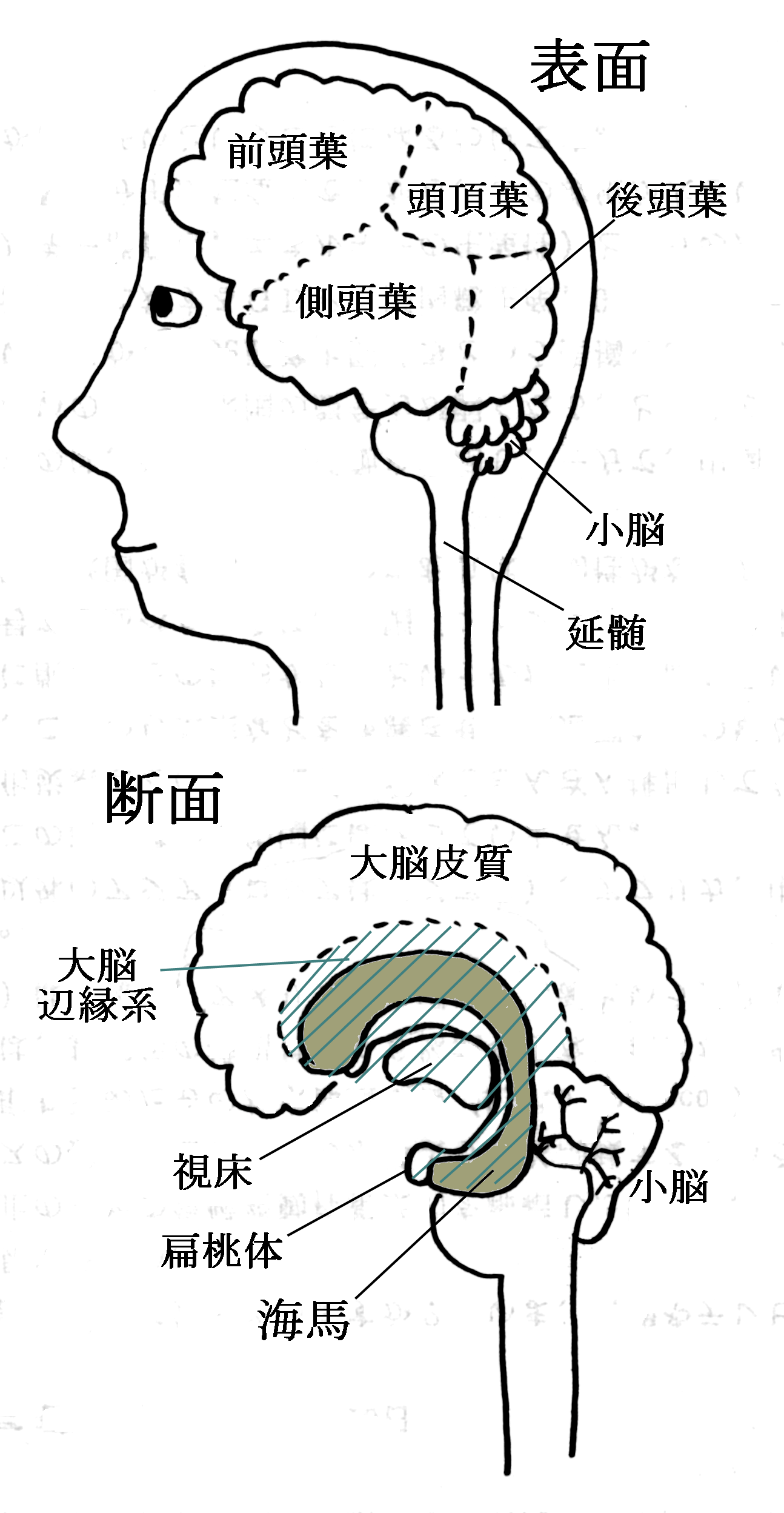 を切ることなく断面を見たり、血液の流れを見た
を切ることなく断面を見たり、血液の流れを見たりすることができるようになりました。楽しいと
き、怖がっているとき、本を読んでいるときなど
に、脳のどの部分に沢山血液が流れているかをリ
アルタイムで見ることができます。
大雑把にいうと、脳の表面に見える大部分は
「大脳
「
号を認知します。「
統合して認知します。「
皮膚からの知覚シグナルに対する応答を調節しま
す。そして「
ると共に、他の3つの領域の機能を調節します。
大脳皮質の内側には「大脳
まとまりの構造体があり、喜怒哀楽、空腹感や食
欲、記憶の取捨選択など
るホルモンなどを生産します。麻薬などで最も影
響を受ける部分だと考えられています。
大脳辺縁系の後ろに「後脳」があります。後脳
には「小脳」「脳幹」「延髄」などがあります。
小脳では、体の姿勢を保つ働きや
したり、運動機能の情報を蓄えています。
人類は、大脳皮質が特に発達しており、生物として基本的な機能を司る内側の大脳辺
縁系を覆い隠すようになっています。
鳥は、運動を司る小脳の割合が大きいそうです。やはり、空を飛ぶとというのは大変な
ことなのですね。
脳の総量は、人間は約1200〜1400グラム程度です。
これらは互いに、500億から1000億の神経細胞(ニューロン)で連絡を取り合っていま
す。このつながり具合、すなわち003号で言った "脳内リンク" が密なほど「頭がよい」
ということになるのです。
海馬と扁桃体
大脳辺縁系の中に、
海馬とはふつう、タツノオトシゴ(竜の落とし子)のことですが、脳のこの部分を海馬
と呼ぶのは、きっと形が似ているからなのでしょう。
目や耳や手などから入ってきた情報は、一旦、この海馬に入ります。海馬では、記憶す
べき情報と捨ててしまうものとに分けて、記憶すべき情報は大脳の各部分に送られます。
もし情報を取捨選択しなかったら、数分で脳の記憶容量をオーバーしてしまうと言われ
ています。
それでは、海馬はどのような基準で情報を選んでいるのかというと、まだ詳しいことは
わかっていません。ただ、なんらかの方法でそれまでの経験(記憶)を参照していると思
われます。
もし海馬を損傷してしまうと、損傷する前までの記憶はありますが、損傷後は、新しく
記憶することができなくなります。5分程度の短期の記憶は海馬を通さずにできるのです
が、長期にわたる記憶はできなくなるのです。実際に海馬を損傷してしまった人は、自分
の行動をメモし続けるということをするそうです。
感情を司る働きをします。扁桃体がないと、恐怖を感じなくなります。扁桃体を切除した
猿は、犬や蛇に平気で近付いていきます。何度噛まれて傷だらけになっても、猿は犬や蛇
を見ると近付いていくそうです。痛い目に遭ったという記憶はあるかも知れませんが、そ
れが嫌なことであるという感情が記憶されないのです。恐怖心や嫌な思いというのは、身
を守るために必要な感情なのです。
記憶と感情が大変密接な関係があることは、実感できるでしょう。激しい感情が伴った
ことはいつまでも覚えています。楽しいことだけでなく、嫌なことも、一杯記憶に残りま
すね。つまり、海馬と扁桃体は互いに連携し合っていることがわかります。これは、気の
持ちようで海馬を "
講演でも、小林教授は「感情豊かに過ごすことが大切」と述べておられました。扁桃体
を活性化することで、脳全体が活性化するというわけです。
海馬は大きくできる
脳の神経細胞は、生まれた時が最も多く、後は1秒に1個位ずつ減っていきます。脳細
胞は新しいものは作られません。ところが、海馬の神経細胞は、次々に死んでいきますが、
次々に生まれてきます。海馬に新しい情報がどんどん入ってくると、死ぬ神経細胞より新
しく生まれる方が多くなって、海馬は大きくなります。大きくなると、更に多くの情報を
同時に処理することができるようになります。
逆に新しい情報が海馬に入らなければ、海馬は小さくなっていき、処理できる情報量も
少なくなりますから、記憶力も衰えます。
人は、窓のない白い壁の部屋のような、極端に情報の少ない状況を強いられると、3日
ほどで脳は自ら刺激を作ろうとします。つまり、幻覚や幻聴が起こったりするのです。或
いは、いらぬことをあれこれ考えたり、突然
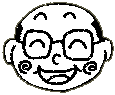 常に新しい風景を見、人と会話を交わす、これが大変良い刺激になるそうで
常に新しい風景を見、人と会話を交わす、これが大変良い刺激になるそうです。ある調査によれば、タクシー運転手の海馬は平均より大きいという結果が
出たそうです。 〟